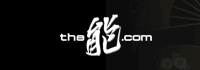 |
 |
 |
| > Top > 支える人びと > 福井芳秀 > エピソード2 |
|
|
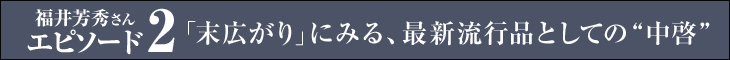
 |
閉じた際に先が広がっているものが中啓(左)と呼ばれ、そうでないものは常の扇(右)と呼ばれる。能舞台ではシテなどの登場人物が中啓を持ち、地謡や囃子、後見は常の扇を持つ 撮影:谷口哲 |
今でこそ伝統芸能だが、能楽は、室町時代には流行の最先端をいく新しい芸能だった。狂言「末広がり」にそんな時代状況が如実に現れて……。
中啓は室町時代にできた最先端商品でした。それは「末広がり」という狂言によく表現されています。この演目は能の製作史からいうと非常に重要です。普通の扇が先にあって、末広が新しくできますが、それを知っているのは新物好きのインテリであり、知識層でした。ですから、庶民の太郎冠者は知らないわけですね。主の大名は知っていて、進物にしたいと太郎冠者に買いにいかせるわけです。ところが太郎冠者は知らないものだから、騙されてしまう。それを見た当時の人たちが皆うなずくというのは、末広が、やはり新製品であったことを示します。
能の世界で使われるものは、今でこそ古典、伝統といわれますが、600年前は能そのものが新しい芸能でした。だから最新の道具を使ったのではないでしょうか? 能の後援者であった将軍や高僧たちも、能役者にそういうものを取り入れさせたと想定できますね。(福井芳秀氏談)
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.