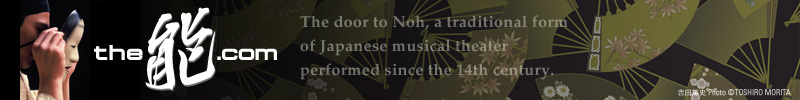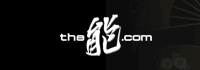| 分類 |
四番目物・雑能、働物(はたらきもの)、切能 |
| 作者 |
観世小次郎信光 |
| 題材・典拠 |
「義経記」巻四「義経都落ちの事」「住吉大物二ケ所合戦の事」が発想の契機だが、それにとらわれない自由な脚色であり、直接の典拠とはいえない |
| 季節 |
秋、冬(11月) |
| 場面 |
前場 |
摂津の国、大物の浦の船宿 |
| 後場 |
大物の浦の海上 |
| 作り物 |
脇座前に舟 |
| 登場人物 |
前シテ |
静御前 |
| 後シテ |
平知盛の亡霊 |
| 子方 |
源義経 |
| ワキ |
武蔵坊弁慶 |
| ワキツレ |
義経の従者 |
| アイ |
船頭 |
| 面 |
前シテ |
若女、深井、増、小面 孫次郎など |
| 後シテ |
三日月、怪士(あやかし)、真角(しんかく) |
| 装束 |
前シテ |
蔓(かつら)、蔓帯(かつらおび)、唐織(からおり)着流し、着付・摺箔(すりはく)、扇。物着(ものぎ)で静烏帽子(しずかえぼし) |
| 後シテ |
白鉢巻、黒頭(くろがしら)、鍬形(くわがた)、袷法被(あわせはっぴ)、着付・厚板(あついた)唐織、半切(はんぎれ)、腰帯、太刀、長刀(なぎなた)をもつ。 |
| 子方 |
金風折烏帽子(きんかざおりえぼし)、長絹、着付・縫箔(ぬいはく)、白大口(しろおおくち)、腰帯、扇、後に太刀をはき、梨子打烏帽子(なしうちえぼし)、白鉢巻、側次(そばつぎ)、着付・厚板にする |
| ワキ |
兜巾(ときん)、篠懸(すずかけ)、縞水衣(しまみずごろも)、着付・厚板、白大口、腰帯、小刀(ちいさがたな)、扇、数珠 |
| ワキツレ |
梨打烏帽子、白鉢巻、側次、着付・厚板、白大口、腰帯、小刀、扇 |
| 場数 |
二場 |
| 上演時間 |
約1時間30分 |