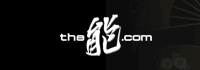 |
 |
 |
| > Top > 名人列伝 > 宝生九郎知栄 |
|
|
宝生九郎知栄(1837年〜1917年)
果てなき芸の道に一身を捧げた「深川さん」
 |
|
宝生九郎ポートレイト(早稲田大学演劇博物館所蔵) |
宝生九郎知栄は、明治維新によって消えかけた能楽の伝統の灯を、盟友・梅若実らとともにあらためて煌々と燃やし、後生に受け継いでいった偉人である。「明治三名人」のひとりとして、芸の気品の高さでは何人も追随し得ないと賞賛され、天性の美声を備えた謡の技量の高さに感嘆されたが、自らに厳しく、終生にわたり果てのない芸の奥の奥、底の底を追求し続けた。芸道への献身と厳しさ、義理堅さと篤い人情、宗家としての強い責任感を併せ持った懐の深い人柄は、流儀を越えて能楽に携わる人々を惹きつけた。その結果、宝生九郎知栄は、危機に瀕していた能楽界全体を牽引し、隆盛への先鞭をつける役割を担うこととなる。
九郎知栄が生まれたのは天保八年(1837年)。当時名望のあった十五世宗家・宝生弥五郎友于の次男であった。弥五郎友于は確かな芸を持ち、時の将軍家から師範役を命ぜられるほど名手の誉れが高かった。九郎知栄も幼少の頃より才能を発揮し、十二歳までに幕府の御用を勤めてかなりの能を舞い、将来を大いに嘱望されたと伝えられる。長男の夭折などもあり、弱冠十七歳で宗家を継いだが、誰からも指弾されることはなく、その技量、人柄ともに素晴らしいものであったことは想像に難くない。
しかし明治維新の激動は、芸道に精進して、ほか一切を顧みることのなかった九郎知栄にも大きな試練となった。明治二年(1969年)に英国皇太子御覧能で「羽衣」を舞ったという記録はあるが、扶持を失い、しばらく能を舞う機会も持てなかったようである。やむを得ず農業を始めようと、板橋の知人を頼って一年ほど過ごした。この頃、梅若実がしきりに訪ね、舞台への返り咲きを勧めた。その熱意を受け、梅若実との親交を深めた九郎知栄は梅若家の舞台に立つようになる。
そして大きな転機となったのは、明治九年(1976年)に梅若実によって裁量に任され、岩倉具視邸で催された天覧の行幸啓能である。楽屋を訪れた九郎知栄は、梅若実の推挙により急遽「熊坂」の半能などを舞い、岩倉具視はその芸力に感銘を受け、以後師事し、稽古を始めることとなる。岩倉を含む有力者の支援も受けるようになり、その後、天覧能、舞台開き能など数々の名演を、梅若実、桜間伴馬ら明治の名人たちとともに繰り広げた。明治三十九年(1906年)の「安宅」を最後に演能から退くが、その後も数々の演能の催しを陰で支えながら、弟子の教育に尽力し、数々の栄誉のうちに、大正六年(1917年)に永眠した。
九郎知栄は宝生流の宗家として、明治26年(1893年)に発足した宝生会を率いるとともに、当時の能楽界全体の支柱となっていた。芸の探求にはことのほか厳しく、流儀には名人どころか上手も達者もいないと断じ、“驕り”を厳しく戒め、果てのない芸の道に一身を捧げることを誓った。後進にもそれを促す言葉が残っている。松本長(ながし)、野口兼資(かねすけ)、近藤乾三(けんぞう)ほか、後に宝生流を盛り上げた多士には、九郎知栄の厳しい芸道への至誠が打ち込まれていたといわれる。
また他流、囃子方、狂言方との連携や切磋琢磨も強く推し進め、舞台に立つ機会を増やし、能楽の発展を後押しした。例えば桜間伴馬の息子・金太郎(後の弓川)には、宝生会の月並能に出演の機会を与え、技量を伸ばす機会としたのである。
いろいろな記録をひもとくと、深川に永らく住んでいたことから、さまざまな立場の人に「深川」「深川さん」「深川の先生」と親しみを込めて呼ばれた記述に遭遇する。そこに、九郎知栄の人徳の一端がしのばれる。
【参考文献】
- 『能楽全書』第二巻 野上豊一郎 編(東京創元社 1981年)
- 『明治能楽史序説』 古川久 著(わんや書店)
- 『謡曲口傳』 寶生九郎 口述(能楽通信社 1915年)
- 『名人寶生九郎』 齋藤香村 編(能楽書院 1929年)
- 『兼資芸談』 野口兼資 著(わんや書店 1953年)
- 『能楽随筆こしかた』 近藤乾三 著(わんや書店 1968年)
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.